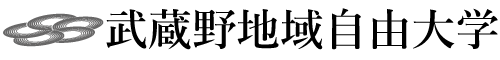科目・講座一覧
武蔵野市寄付講座
2025年度 後期
武蔵野市の寄付によって、大学が開設する特設講座です。
後期は亜細亜大学・成蹊大学・東京女子大学・日本獣医生命科学大学・武蔵野大学の5大学で開講します。
※講師・日程・テーマ等変更になる場合があります。
申込み締切日:令和7年7月24日(木)必着
亜細亜大学
「日本経済の課題と展望―人口減少下でも国民が輝く国を目指して」 |
1990年代のバブル崩壊以降、経済政策の最重要課題の一つとされてきたデフレ経済からの脱却が視野に入りつつあるが、そのトンネルの先には、より困難な構造的な課題が山積している。急速に進む少子高齢化、グローバル化の進展と変質、デジタル化や脱炭素化への対応などの課題に適切に対応し、包摂的で持続可能な経済成長を実現していかなければ、長期的には、日本経済は様々な経済・社会サービスの水準を維持することすら難しくなる。かつて、日本の経済システムは、終身雇用による「人」を中心にした経営で、高い経済成長と格差の少ない社会を実現し、世界から賞賛された時期があったが、現在では、企業のパフォーマンス、雇用の質、所得再分配、イノベーション力など様々な面で綻びが目立つようになっている。また、日本はこれまで格差の少ない社会を構築してきたが、現在では雇用保障のない非正規雇用が大きな割合を占めるようになり、そうした労働者はセーフティネットでも十分カバーされず、相対的貧困率も先進国の中で高い水準になっている。こうした日本経済の諸課題に関して、経済・金融の各分野の専門家・実務家を迎え、日本経済の現状認識と今後の対応の方向性について話を伺う。その上で、今後人口減少がさらに進む中でも、国民が仕事のやりがいや生活することに満足感を得られ、輝くことができる社会の実現に向けた方向性を参加者とともに検討する。
各回の講座のテーマや日程につきましては、寄付講座のチラシをご覧ください。
▲ポイント付与対象講座です。9回以上出席で1ポイントが付与されます。
成蹊大学
「インフレ時代の資産形成」 |
これまでわが国では、バブル崩壊後、長期間にわたってゼロインフレ(もしくはデフレ)の時代が続いていた。2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵攻後、数%程度のインフレが発生しており、今後もこのトレンドは継続するとの見通しも出ている。このような環境下、預貯金を中心とした資産形成を続けていくと、インフレによる金融資産の実質価値の目減りが懸念される状況が生じている。本講座では、このような観点から、各分野における有識者によるオムニバス形式での講義を通じて、年金制度や証券市場・証券投資に関する基礎知識を理解するとともに、資産形成のあり方についてご一考いただく機会をご提供することを主な目的とする。
▲ポイント付与対象講座です。10回以上出席で1ポイントが付与されます。
各回の講座のテーマや日程につきましては、寄付講座のチラシをご覧ください。
東京女子大学
「文化保全の国際的取り組み―つながりと格差の文化人類学―」 |
世界の共通目標である持続可能な発展の実現のためには、文化の保護・保全は重要な課題の一つとなっている。この授業では、文化保護・保全に関する国際連合の動向をふまえながら、社会経済的圧力に対して脆弱性を抱える諸文化社会において、持続可能な発展の実現に資する文化保全がいかなる状況にあるのかを実例から学ぶ。そうした諸文化社会において、次世代が文化的知識や知恵を享受し継承していくうえでの課題、文化保全活動上の南北間格差がいかに生じるのかを考えていく。
▲ポイント付与対象講座です。11回以上出席で1ポイントが付与されます。
各回の講座のテーマや日程につきましては、寄付講座のチラシをご覧ください。
日本獣医生命科学大学
「食文化論」 |
「食文化」の学問領域は、食物の生産から人の胃袋に入るまでの、食生活全般に及び、食に関するあらゆる文化面を対象としている。本年は、第二次世界大戦中のオランダ首都アムステルダムで「隠れ家」生活を送ったアンネ・フランクが記した『アンネの日記』を教材として取り上げる。
▲ポイント付与対象講座です。8回以上出席で1ポイントが付与されます。
各回の講座のテーマや日程につきましては、寄付講座のチラシをご覧ください。
武蔵野大学
「みんなが幸せな世界を創る『ウェルビーイング学』入門」 |
2024年4月、武蔵野大学に世界初のウェルビーイング学部ウェルビーイング学科が発足しました。ウェルビーイングとは、幸せ、健康、心と体の良い状態のことです。本学科では、科学や哲学を基盤にして、世界中の人類や動植物が幸せな世界を構築するための新しい学問を展開しています。ウェルビーイング学科には、工学、理学、哲学、宗教学、心理学、社会学、対話、コーチング、教育学、経営学、経済学など、さまざまな学問を基盤にウェルビーイング学を深める教員が集まっています。本講座では、14名の教員がオムニバス講義を行い、多面的な学問ウェルビーイング学について概説します。新しい学問ウェルビーイング学の新風をぜひお楽しみください。
▲ポイント付与対象講座です。10回以上出席で1ポイントが付与されます。
各回の講座のテーマや日程につきましては、寄付講座のチラシをご覧ください。
| 対象 | 武蔵野地域自由大学学生および18歳以上の市内在住・在勤・在学の方 |
| 定員 | 各大学50名(超えた場合抽選) |
| 費用 | 各大学5,000円(資料代) |
| 申込 方法 | 以下の①~④のいずれかの方法でお申込ください。 ①ハガキに[希望大学名、住所、氏名(フリガナ)、電話番号、生年月日、武蔵野市在勤・在学の方は勤務先・学校名、自由大学学生は学籍番号]を明記のうえ、自由大学事務局「寄付講座」係へ郵送 ②直接武蔵野プレイス3階自由大学事務局窓口にて申込み ③「武蔵野市文化・スポーツ・生涯学習ネット」から申込み *インターネットで申込みの場合、抽選結果は各自申込サイトで確認してください。 (結果公開期間:8月5日(火)~各大学初日) ④自由大学学生の方は、自由大学事務局へ電話(0422-30-1904) |
| 申込期間 | 6月27日(金)~7月24日(木)必着 |
| 受講 決定後の 提出物等 | 当選が決定した方には提出方法など詳細を郵送でお送りします。 ①資料代 各大学5,000円 ※必要書類提出時に、武蔵野プレイス3階自由大学事務局でお支払いください。 ②受講同意書 抽選結果通知に用紙を同封します。 ③健康診断書(結果票)のコピー 1大学につき1部(令和6年8月1日以降受診のもの。健康診断書の必要事項に関する詳細は、自由大学通信vol.87(令和7年6月27日発行)2ページでご確認いただけます。) ④証明写真 1大学につき1枚(受講証用。ただし、成蹊大学・東京女子大学は不要。スナップ写真は不可。武蔵野大学は白黒写真不可。サイズ等は当選のご案内でご確認ください。 |
| 提出期間 | 8月5日(火)~8月18日(月) |